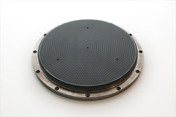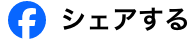常識を変える水栓は、きっとつくれる。
祝! 建築設備技術遺産認定
「アクアオート」の誕生と進化を支えた想いとは。
<進化編>
1984年に誕生した自動水栓「アクアオート」。初代発売以降、技術的な困難や普及の課題を克服しながら、「アクアオート」はその節水性やユーザビリティをますます高めていきます。今回は「進化編」として、その技術革新の歴史にクローズアップ。さらに、初代から進化を見守り続ける開発者たちが「アクアオート」の今後に期待していることもお聞きします。

-
1985年~要素機構設計課にて「USシステムA型」モデルチェンジを担当。
-
1987年~機電設計課にて「アクアオート」の開発を担当。
-
1990年~機電開発課にて「初代ネオレストEX」開発、「NEW CS大便器」の開発を担当。
-
1993年~衛陶機器開発一課へ異動。 ロータンク内部金具(fJ)開発その他を担当。
-
2002年~非住宅商品開発グループへ異動。小便器のフルモデルチェンジを担当。
-
2004年~健康商品設計Gにて「インテリジェンストイレ」の開発を担当。
-
2008年~パブリック商品開発部にて商品モデルチェンジなどの業務を担当。

-
1982年TOTO株式会社入社。金具設計第一課にて、主に小便器自動洗浄、自動水栓など機電商品の開発や設計業務全般に携わる。
-
1985年~茅ヶ崎工場に転勤。特機設計第二課にて大小自動便器、自動手洗器の開発をはじめ、全自動洗面器など機電のシステムや浴室向けTVなどの商品開発に従事。
-
1993年~本社 金具機電開発課にて、電子水栓の新商品開発に携わる。
-
2009年~中国駐在(東陶上海、東陶大連)。
-
2013年~機器水栓生産設計部にて機器商品開発及び水栓生産設計業務に携わる。
節水の決め手は「角度」! そして「空気」も。
ここからは、「アクアオート」2代目以降の進化の歴史についてお話いただきたいと思います。現在はもう7代目!改良された点はたくさんあるかと思いますが、大きくポイントを挙げるとすればどういった点になりますか?
濱中 まずは「節水性」です。「アクアオート」は最初から節水を目的とした商品です。パブリックシーンで多くの人に使われますから、お施主様にとってはやはり節水性が訴求ポイントになります。それから、エコという視点では「節電」も挙げられますね。最後に、センサーをいかに「小型化」するか。節水・節電・コンパクト化。この3つが、大きな進化のポイントです。

濱中
考えるべきは、「いかに水を有効に使って、少ない水量できちんと洗えるか」。たとえば吐水の角度です。まっすぐ90度に吐水すると、差し出した手の先端にしか水は当たりません。でも、少し角度を下げて斜めに吐水すれば、手に当たる範囲が広くなりますよね。
最初は15度まで角度を小さくしてみました。確かに手に当たる範囲は広いのですが、なぜか葬儀場などからクレームが来てしまって。
濱中
そうなんです。水が水平方向に出ることが普通ではなく、使う方も戸惑いがあったのかと思います。だからそのあと、吐水角度を30度に変更しました。今でも水栓商品の吐水角度は、基本的に30度のままなんですよ。
また、TOTOが独自に開発した「ハイパー泡沫」という技術があって、水に空気を含ませることで少ない水で洗い心地を保てるようにしました。
田中
そうです。もともと吐水口には泡沫キャップが付いていたのですが、空気を巻き込みやすい形状に改良して、泡の量を増やしたんです。水を少なくするだけだと、手に当たる力が弱まるので、あまり「洗った感」がしないんですよ。その物足りなさを、空気の感触で補うんです。
当初は、水が少なくなるとその分吐水時間が長くなるのでは? と懸念の声もあったのですが、実験で確認してみるときちんと節水できていることが分かりました。

電気を使う自動水栓。でも実は、
“電源なし”で動いている!?
節電は、使用電力の省エネ化、ということでしょうか。
濱中
そうですね。まず、超省電力で動くセンサー・コントローラをつくりました。1989年に出た2代目は、バッテリーでバルブを動かしているんです。バッテリーで動くバルブなんて当時は世の中になかったので、その開発が一番難しかった。でもちょうどその頃、社内にエレクトロニクスの技術者が増えていたこともあり、独自開発によって乾電池で動く「アクアオート」が誕生しました。
ところがしばらくすると、乾電池式だとその交換が面倒だという声も出てきて……ならば、自己発電できればいいのでは? と。最終的に電源レス化を実現しました。
濱中
2001年に出た5代目以降は、すべて水力で発電し、その電気を使っていますね。そのおかげで、設置できる場所が格段に広がり、電源がない場所でも取り付けられるようになりました。
また、学習機能も高まりました。使用状況をコントローラが学習できるようにして、人が使わない夜間などは回路を眠らせ電力消費を最小限にしました。今はほとんどの商品で当たり前ですが、一週間分の行動パターンを記録して、使用パターンに合わせて作動を最適化させるんです。バッテリー化から始まって、今ではそんなところまで進化しましたね。
濱中 これも、回路系を新しくしたことで実現しました。それまでデザイン性や使い勝手を犠牲にしてきた部分もありましたが、小型化に成功して随分改善されました。そうそう、初代の頃、センサーが洗面ボウルの素材を感知してしまう問題があったでしょう?(※誕生編参照)センサーの位置を変えることでまたその問題が生じたのですが、今度はセンサーに光板を入れることで解消できました。ステンレスなどにセンサーが当たると、光の波がビシッとまっすぐに返ってくるんです。もしこれが手だったら、乱反射した波になる。そこで、まっすぐ返ってくる光には反応せず、乱れた光だけに反射するようにしました。