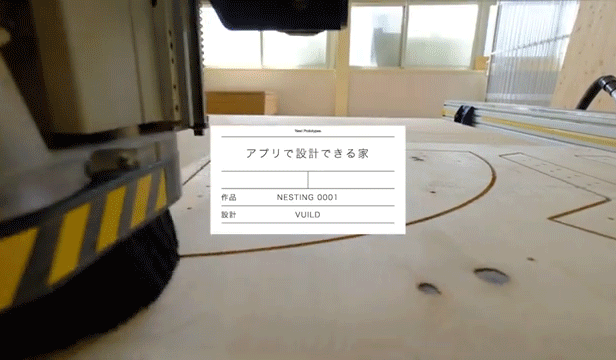特集

2022年 夏号 プロトタイプの野心‑ CaseStudy#1 ‑大量生産と一品生産の狭間
作品/「NESTING 0001」
設計/VUILD
秋吉浩気さんは、自分を投影した作品設計ではなく生産・流通・設計の基盤、体系やビジネス、新しい文化や産業をつくることも今の建築家にとって重要な仕事だという。ついにかたちとなった「NESTING」シリーズの第1号に込められた想いとは。
取材・文/植林麻衣
写真/黒部駿人、川辺明伸(*印、ポートレート)



「建築家になりたい」
秋吉浩気さんは子ども心にこんな憧れを抱いて建築の道に入った。それが時を経て、「ハウスメーカーをやってみたい」と思うようになり、2021年にデジタル家づくりプラットフォーム「NESTING」を立ち上げ、その試作となるプロトタイプを建設する。
住宅市場で分譲住宅が占める割合は6割弱、注文住宅は4割近く、そして建築家が手がける住宅は数%ともいわれる。この量の世界に、秋吉さんが主宰するVUILDはどう切り込もうとしているのだろう。
体験型コンテンツとしての家づくり
「初号機」となるプロトタイプが立つのは、摩周湖・屈斜路湖がある自然豊かな北海道川上郡弟子屈町(てしかがちょう)。別荘である母屋の離れとして計画された平屋で、わずかに傾斜する外壁に、翼を広げたような屋根がのる独特のたたずまいは、量の追求のために合理化を図り、無味乾燥なデザインに陥る従前のプロトタイプ住宅とは一線を画する。そのカギとなるのが、松葉杖型の構造体「ベッキーユ」である。
「ベッキーユ」は、フランスの建築家ジャン・プルーヴェが命名した構造体だ。構成パーツは3軸CNC加工機「ShopBot」でプレカットし、合板を無垢材で両面から挟んでボルトで一体化させる。この「ベッキーユ」を1間おきに立てたあいだに3×6の合板を加工したリブ付きの耐力壁パネルユニットを落とし込むと、大きな無柱の内部空間が生まれる仕組みだ。上棟は約1日、サッシを含む軀体工事は3日ほどで完了する。
今回建てた離れは、人が集うことを目的としており、森を気持ちよく望める雁行型に。そのプランは、どのような暮らしをしたいかヒアリングをして方針を固めたうえで、建主自ら描いたものがベースとなっている。開口部の位置など空間の質を左右する要素についてはプロとしてアドバイスをしているが、「NESTING」においては、主体はあくまで建主。完成品を手に入れるのでなく、自ら家づくりの楽しみを味わいプロセスを体験する価値は大きい、というのが秋吉さんの考えである。
今後は開発したアプリを用いて、さらに建主の参加を加速させる。1間をグリッドとしてプランをシミュレーションでき、開口部の位置やインテリアの仕様も細かい変更が可能に。画面上では見積もりが同時に算出されて、デザインとコストをリアルタイムで擦り合わせながら自らデザインできる。また建主を主体に据えることは、コミュニケーション・コストの削減というメリットもある。
「ライフスタイルを表現したアート性のある住まいがほしいけれど、建築家に頼むのは敷居が高いし時間もかかって億劫、とはいえ工務店のデザインでは物足りない。そんな潜在的なニーズが一定数存在するのです」と秋吉さん。従来の一品生産型の注文住宅では、建主の要望を聞いて建築家が図面を引き、工務店が見積もりを出すのに1カ月は要していたが、「NESTING」はリアルタイムで金額を弾き出す。プレファブ住宅のようなコスト感と建設スピードをもちながら、建築家がデザインした作品ならではの質を備えた注文住宅――大量生産と一品生産の狭間に「NESTING」はその姿を現した。



ものづくりを個人の手に取り戻す
秋吉さんが生まれたのは1988年。建築家が住宅不足という社会的課題に応えるべくプロトタイプを手がけたことが、遠い過去になった時代だ。どのような経緯で「NESTING」は生まれたのだろう。
「建築学科に入ったものの、卒業したら修士に進み、そのままアトリエ系事務所で修業・独立するような“建築家双六”が嫌で。大学生活の節目を迎える頃に東日本大震災が起こったのですが、建築家は仮設住宅をつくることしかできず、本当に社会にコミットした存在なのか、職能に疑問を抱くようになったのです」
さらに背中を押したのが、ほぼ時を同じくして出合った1冊の本の存在だ。3Dプリンターなどのデジタルファブリケーションで誰もがメーカーになれる可能性を綴った、クリス・アンダーソンの『MAKERS21世紀の産業革命が始まる』(NHK出版)である。
規範的な建築家教育に見切りをつけて、ソーシャル、クラフト、デジタル、ビジネスを包含することで建築と社会を結べないかと、大学院でデジタルファブリケーションを学ぶ。修了を控えた頃、スタートアップ支援を行う起業家と出会うがすぐにサポートを得られたわけではなく、「“何を話しているのかさっぱりわからない”と言われて、禅問答のような対話を半年間続け」、17年にVUILDを立ち上げるに至った。
設立に際して掲げたのは「建築の民主化」。消費するだけではなく、誰もがつくり手となり、ものづくりを楽しめる環境づくりに着手しようと、まずは「ShopBot」の国内販売代理店を開始する。このアメリカ生まれのCNC加工機は、個人でも自由に技術を手に入れられることをモットーに開発されたリーズナブルなもので、全国各地の林業・製材関係者に口コミで広がることに。そして「木製ものづくりを、速く、安く、デザイン自在に」と謳ったクラウドプレカットサービス「EMARF」の開発にも着手する。
「ShopBot」と「EMARF」を用いてパブリック・ファニチャーから建築へ活動を広げ、19年には富山県南砺(なんと)市利賀(とが)村で、デジタルファブリケーションと地場材を活用した合掌造の「まれびとの家」を竣工させる。
こうした一連の活動の延長線上にあるのが、21年5月に発表した「NESTING」だ。開発期間はわずか3カ月。ハウスメーカーの研究開発と比較すると、驚異的なスピードである。試作としてプロトタイプを1棟建てたいと公募したところ、コロナ禍中の巣ごもり需要もあり50件以上の問い合わせが来た。記念すべき1棟目には、3桁を超える量を目指す意図を込めて「0001」とナンバリングを。事業展開にあたっては、第三者割当増資資本金と起業して間もない企業に出資するエンジェル投資家により、累計約5億円を調達した。




プロトタイプという見果てぬ夢を飛び越えて
「ShopBot」が生産基盤、「EMARF」が流通基盤とすれば、「NESTING」は設計基盤だ。その核となる「ベッキーユ」は、「どこでも・誰でも」つくれることを目指した構造体で、「ShopBot」と、大量流通する合板、そして地元の木があればよい。パーツの規格も手のひらでつかめる程度の幅で、厚みも家具並み。こつこつ組み立てればふたり一組で大断面の集成材にも似た構造材の製作を可能とする。通常の集成材工場なら数億円の設備投資が必要となるところ、「ShopBot」なら2棟建てれば元手が回収できるのだ。「夫婦ふたりで営むような小ぢんまりとした製材所で、近くにある材料を自分たちの手で加工できるようになれば」と秋吉さんは語る。
「ShopBot」の販売数は100台を超えた。いわば小さな点のような生産拠点で、ハウスメーカーの一極集中型の大規模施設とは対極的な存在だ。また「NESTING」は要件に応じて形態を変える柔軟性も孕んでおり、セカンドハウスやアトリエ、スタジオ、コワーキングスペースなどの需要に応えることも想定、現在は住宅以外のプロジェクトが進行中だ。今回のプロトタイプはすべての原点となるもので、全国の小さな拠点群がこの雛形をもとに新たなかたちを展開、自立分散型の生産プラットフォームとなることで「ものづくりの流通量」を増やすことを秋吉さんは展望している。
そのビジョンにおいて、建築家は黒子的な存在だ。「ただ、それも今ならではの建築家のあり方だと思っていて。建築家がデザインするのは自分を投影した作品ではなく、生産・流通・設計の基盤。体系やビジネス、新しい文化や産業をつくることも、建築家としての職能だと思っています」。そんな秋吉さんの原動力は、「好きなように働いて、好きなようにものをつくって、好きなように生きる」という想い。
オンリーワンを設計することがアイデンティティでもあった建築家にとって、量を満たすことを前提としたプロトタイプは、アンビバレンツな見果てぬ夢のようなもので、手を伸ばそうとしても高い壁に阻まれるのが常だった。しかし今、その壁は、デジタル技術と「好きなように生きたい」というひとりの建築家の想いが掛け合わさり、軽やかに飛び越えられようとしている。
設計アプリケーション

デジタル家づくりプラットフォーム「NESTING」での設計を実演する秋吉さん(*)。


実際の画面(β版)。クリックして間取りを描くと瞬時に3Dが立ち上がる。4月に正式版がローンチされた。
https://nesting.me/
ベッキーユの構法

柱と跳ね出しの梁を一体化した木材ユニット。「ShopBot」で切り出したスギ材で合板を挟んだものを並べてビス留め。接着剤を補助的に用いる。
-

秋吉浩気Akiyoshi Koki
あきよし・こうき/1988年大阪府生まれ。芝浦工業大学工学部建築学科卒業後、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科X‒DESIGN領域にてデジタルファブリケーションを専攻。2017年にVUILD創業。おもな作品=「まれびとの家」(19)、「カヤックガーデンオフィス」(19 )、「CAMPPOD」(20)など。