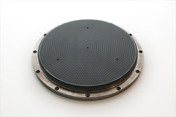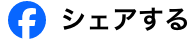一戸建て住宅リフォームのヒント
リモデルライブラリー
「キッチンやトイレなど水まわりの設備を移動して、生活動線をスムーズにしたい」「日がさんさんと降り注ぐリビングをつくりたい」。あなたがリフォームで実現したいことは何ですか?
あなたが一戸建てにお住まいの場合、間取りを大幅に変更したり、開放的な吹き抜けをつくったりして、見違えるような住空間を手に入れることができます。さらに、耐震性や断熱性を高めるなど、住まいの安全性や快適性を高めることもできます。その一方で、リフォームでは建物の構造や建築基準法による制約もあります。まずはできることを確認しましょう。
一戸建てリフォームでできること・できないこと
自由度の高い一戸建てのリフォームですが、「そうは言ってもどこまでできるの?」という疑問が出てきますよね。ここでは、ご希望の多いリフォームのテーマを取り上げて、「ここまでできる!」をご紹介します。
間取り変更はここまでできる!

部屋の位置を変えたり、壁を取り払って複数の部屋を1つにするなど、一戸建てのリフォームではできることがいっぱい。けれど、間取り変更ができるかどうかは、ご自宅の建築工法によって異なります。大まかには、建物を支えているのが柱なのか壁なのかの違いがポイントです。比較的自由度が高いのは、木造軸組工法や鉄骨系プレハブ工法、重量鉄骨造りなど。一方、制限が増えてしまうのが木質系・コンクリート系のプレハブ工法、壁組工法(ツーバイフォー)工法などです。
水まわりの配置はここまで変えられる!

キッチンやトイレ、浴室といった水まわり設備の移動や増設は難しそうなイメージがありますが、一戸建ての場合、比較的ご希望に沿ったリフォームが可能です。水まわりの設備を一新するのはもちろん、「シンクの向きを変えて対面式にしたい」「トイレの数を増やしたい」「浴室を2階に設けたい」など、"家族が増えた"、"二世帯同居することになった"といったライフスタイルの変化にも対応できます。
窓・ドアの移動と増設はここまでできる!

窓や玄関ドアの移動・増設を行うことは可能です。ただ、位置を移動する際は建物構造を踏まえて行う必要があるので、リフォーム店に相談してみてください。
また、「防火地域」「準防火地域」にお住まいの場合、玄関ドアには耐火性能の高い材質を選ぶ必要がある場合も。地域によっては、デザイン性だけで選ぶことが難しいケースがあることをお忘れなく。
防火地域・準防火地域とは?
主に、建物が密集する都市部の多くが、防火地域・準防火地域に指定されています。該当地域では万が一、火災が起きたときに延焼を防ぐため、建物の構造と材料に一定の制限が設けられています。
コンセントの移動・増設はここまでできる!

ここ数年、生活に必要な電化製品が格段に増えたことで、築年数の古いお住まいでは「コンセントの数が足りない」「タコ足配線でしのいでいるけれど心配」というお声が目立つようになりました。コンセントを増やしたり位置の移動は比較的、自由にできます。
増設する場合は、電力会社との契約アンペア数の見直しも同時にご検討ください。
増築はここまでできる!

建物はその土地ごとに決められた「建ぺい率」「容積率」によって、敷地面積に対してどの程度の規模の建物を建てられるかが決まり、増築ができるかどうかもそれによって変わってきます。
一方で、「うちは新築時に建ぺい率の制限いっぱいに建てたから無理だろう」とお考えの方でも、用途地域の変更などその後の規制緩和で増築が可能になっている場合もあるのでリフォーム店に相談してみてください。
あなたの家の建物構造をチェックしよう

リフォームでできることは建物構造が深く関わってきますので、最初に確認をしておくとスムーズです。自分で確認したい場合は、ご自宅を購入・建築された際に渡された「建築確認申請書」「建築確認済証」「設計仕様書」「建築確認通知書」といった書類を見てみましょう。また、「設計図面」があれば、構造をより正確に確認ができます。
そのほか、ご加入の火災保険の証書にもリフォーム検討に必要な情報が記載されています。わからないときは、リフォーム店に「構造を確認しながら相談に乗ってほしい」と伝えてみて。




法的な制約もチェックしよう
リフォームにも建築基準法が適用され、この法律の範囲内で実施するよう定められています。また、増築などを伴う大規模なリフォームの場合、役所に確認申請を提出し、事前に許可を得る必要があります。いずれもリフォーム店がきちんとリードしてくれますが、ここではどんな制約があるのかいくつかご紹介します。リフォーム完了の期日が決まっている方やお急ぎの方は、早めにリフォーム店に相談するといいですね。
増築する場合

敷地ごとに、建物を建てられる面積「建ぺい率」が定められています。例えば10m2の土地で建ぺい率が70%の場合、建物が建てられる建築面積は7m2が上限となります。それと同時に配慮しなくてはならないのが、増築後の総床面積を「容積率」の範囲内に収めること。容積率とは敷地面積に対する建物の総床面積のことで、建ぺい率と同様にあらかじめ決められています。容積率の場合、2階建ての住宅では1階と2階を合わせた面積で計算する必要があります。
さらに、住宅の日照、通風などを確保するための「北側斜線制限」「道路斜線制限」などいくつかの規制によって、建られる建築物の高さに制限があり、階数を増やす増築が難しい場合も。
これらの条件を満たす増築プランを立てる必要があります。
「建ぺい率」とは?
敷地面積に対する建築面積の割合のこと。建物を建てる際、その敷地の何%まで使えるのかを指します。
「容積率」とは?
敷地面積に対する建物の延床面積の割合のこと。その敷地に対してどれくらいの広さ(総床面積)の家が建てられるかを指します。
大規模リフォームの場合

大規模リフォームを行う場合、確認申請が必要になることがあります。その際に直面しやすい問題として、「道路幅員制限」があります。これは、建物を建てる敷地が、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというもの。災害時の避難経路として、消防車や救急車が通る道を確保するのが目的です。制約がなかったころに建てられて、基準を満たしていない住宅も少なくありませんが、現在はこれをクリアする必要があるのです。
ご自宅前の道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心線から2mの位置が道路境界線とみなされ、その分建物を建てられる面積が減ってしまうこともあります。
外まわりをリフォームする場合
ご自宅のある地域が「防火地域」または「準防火地域」に指定されている場合、外装や窓などの材料に制限が設けられています。これは、市街地における火災の危険を防ぐために制定された地域のことで、建物が密集しているエリアが該当します。このエリアの建物は、鉄筋コンクリート造などの「耐火構造」や、鉄筋コンクリート造などの建物に防火性の高い窓や出入り口を設置した「耐火建築物」であることが建築条件に含まれています。外壁や屋根など外まわりのリフォームをお考えの方は、ご自宅がその地域に指定されているかどうかを調べておくといいですね。
キッチンなど火を使う部屋をリフォームする場合
ガスコンロのあるキッチンなど火を使う部屋の壁や天井、作りつけの棚には、「燃えにくい素材」を使うよう建築基準法で決められています。具体的にはコンクリートやレンガ、陶磁器質タイル、金属板、ガラス、一定の厚さのある石こうボードなどです。
一戸建てのリフォーム実例
一戸建てのリフォーム実例をご紹介します。あなたのリフォームの夢を膨らませるために、ぜひご覧ください。
${title}
${building.name}
${cost}
- ${case_unit_type}
${remodel_club.store_name}
通信エラーのため、出力に失敗しました。