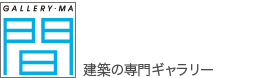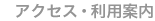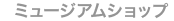- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
- スマホ画像ダウンロード

今回は特別編として、2月8日に開催したギャラリートークの開催報告をまとめていただきました。建築家の中山英之さん、本展のためにマンガを書き下ろした漫画家で建築家の座二郎さんと吉村靖孝さんの3人で、「二次元ケンチク、三次元ケンチク、四次元ケンチク」という不思議なタイトルの下、繰り広げられたトークの様子を、前半の会場ツアーの模様と合わせて前後編でお届けします。
(本来はトーク後にギャラリーツアーを行う予定だったが、出張先から会場に向かっていたゲストの中山英之さんの到着が降雪による新幹線の遅延で開始時間に間に合わず、急遽、先にギャラリーツアーを実施することになった)
吉村:僕は2年前に脳出血を発症しました。その直後は言葉もまともに出てこないような状態でしたが、3カ月ほど入院して退院したころに、当時、TOTOギャラリー・間の運営委員だった塚本由晴さんからメールがあり、「(吉村さんの)展示が決まったんだけど、できるか?」と聞かれ、「できます」って、なぜかわからないけれど自信をもって答えたんです。

この展示では、7人の漫画家に僕の作品を描いてもらっています。実は、僕は漫画が好きというわけではありません。でも本展では建築家の作家性というものを問うために、漫画家という別の作家たちに僕の作品を預けてみました。今日はその漫画家の1人である座二郎さんに来てもらっています。
座二郎:今回の展示、および図録では最後、7番目の漫画を描いています。私にとって吉村さんは大学時代からの先輩で、ずっと憧れの建築家でもあり、吉村さんが漫画で個展をやるらしいという話を聞いたとき、俺に声をかけてくれなかったらどうしよう、建築も漫画も両方やっているのは俺しかいないはずだけど、と思っていたら、ちゃんと声をかけてくれてホッとしました(笑)。
吉村:ギャラリーの下の階(3階)では、僕の7つの作品をテーマにした漫画を展示しています。実際の漫画はB4判の大きさで描かれていますが、壁沿いの台の上にはその拡大版を展示しています。拡大すると、小さいサイズのときは気づかなかったことに気づいたりします。
座二郎:これを見て、建築の図面は実際に建てるものを何分の1かに縮小して表現することとの対比で漫画を大きくしたのかなと思いました。漫画の成果品はB4サイズ、あるいは印刷されたものですから、あえてそれを拡大するというのは非常に面白い試みだと受け止めています。
吉村:建築の図面は1/1が最大で、普通は1/2、1/5とどんどん小さくなっていく。大きくすることはないものね。
3階の中央ゾーンでは、7人の漫画家に描いてもらった漫画を読んで僕が考えたことを展示物として、それが7つ並んでいます。図録の漫画の掲載順に番号を振っていて、それは僕の作品の古いもの順でもあります。1番は「Nowhere but Sajima」の窓で、2秒遅れの時差がある世界を映し出しています。コルシカさんが描いてくれた「Nowhere but Sajima」の漫画が時差を取り込んでいるので、このような展示にしました。

座二郎:「Nowhere but Sajima」は海側の立面の窓に特徴があるわけですが、コルシカさんの漫画には、実際のその立面の窓を使って漫画の“コマ割り”をしているページがあります。コマ割りという時間が進んでいくものを、吉村さんはプログラムでつくって現出していて、私はこの展示が一番、「おおっ」と思いました。
吉村:コマ割りでいうと、ポスターも7つのコマ割りになっていて、各漫画家に1コマずつ漫画を描いてもらっています。そのポスターのコマ割りがこのフロア(3階)では天井に描かれていて、つまり、ポスターのコマ割りと展示の配置が同じになっている。
座二郎:展示の平面図が漫画のコマ割りになっているということですね。
吉村:2番は「Red Light Yokohama」です。横浜黄金町のかつて風俗店だった10㎡の一室を改装したとき、部屋の手前は真っ白、奥は緑に塗り分けました。それで奥の部屋で緑の壁を30秒くらい凝視した後、白い部屋に移動すると、人間は白い部屋を緑に見ようとして脳が勝手に、緑の補色であるピンクのフィルターをかけるので、白い壁がピンクに見える。「補色残像効果」という現象で、それを川勝徳重さんが漫画にしてくれているのですが、建築家がちょっと悪者に描かれている。
座二郎:めちゃくちゃ悪者に描かれていますよね(笑)。
吉村:川勝さんの漫画を見てショックだったというか、いい気づきになりました。自分は良いことをしたと思っていたけれど、なんかわからず屋の男として描かれていますからね。
漫画の登場人物がジャングルの中で、緑からピンクへの補色残像の現象を発見するので、展示も、この緑の中に入って少し経ってから外に出ると、白いものがピンクに見えるようにしたんだけど……あまりきれいにピンクに見えない(苦笑)。白いものがないと難しいのかな。
3番は「窓の家」で、漫画は德永葵さんが描いてくれました。德永さんは漫画家ではなく画家で、絵に漫画が入っているというか、不思議な絵を描く人です。
座二郎:白い紙に漫画風のキャラクターを線描きして、その紙を折って、自然や日常の風景に溶け込ませているような絵画を普段は描かれているんですよね。
吉村:德永さんの漫画には微妙に形の違う「窓の家」が出てくるので、僕はそれを二つ折りにした、飛び出す絵本みたいな展示物を作りました。
4番は鉄骨造の既成倉庫の中に木造の構造体を挿入した「フクマスベース」という僕の作品を三池画丈さんが見て、木造の構造体が命を持ってうごめいているようなシーンを描いてくれたので、それをここに再現しています。
5番の「ホームトゥーゴー#001」は軽トラックの荷台にこういう物体を載せて、各地で暮らせるモバイルハウスです。宇曽川正和さんはその物体の中に、ぐにゃりと形の定まらない人工生命体を入れて、話が展開するにつれ形が明らかになるという世界を描いてくれています。
6番のこれはメグマイルランドさんが漫画の中で生み出したキャラクターで、マックスという名の雄鳥。僕の作品「滝ヶ原チキンビレジ」に住んでいるという設定です。「滝ヶ原チキンビレジ」はイデー創業者の黒崎輝男さんからの依頼でつくった2つの鶏舎で、黒崎さんが石川県小松市の里山で進めている自立循環型の小さなコミュニティ「滝ヶ原ファーム」で使われています。
座二郎:漫画の中では鳥のスケールと人間のスケール、両方の話が出てきて、ニワトリが人間と同じ大きさになる。漫画の読み解き方としては、人間が小さくなると言うべきなのかな。漫画の中で鳥は鳥として鳥の建物の中で暮らしていて、あのスケールを人間のスケールに合わせて拡大するとこういうことだよというのを、この展示では表現しているんですよね。
吉村:最後は現在設計中の「VERTIPORT(バーティポート)」という、空飛ぶクルマのための空港です。
座二郎:これの漫画は私が描きました。描いた漫画は最終的に本の形になって発表されるけれど、その漫画に関連した展示があることも最初からお聞きしていたので、私は漫画の制作過程を面白く見せられたらいいのではないかと思ったんですね。それで、漫画の原稿にいろいろな紙を使っています。普段もわりとこれに近い作り方をしていて、例えば黒ベタで塗るよりも黒い紙を裏に貼るほうが均一な黒が出せるとか、単にグレーにするのではなく銀紙を使うとか、いろいろやって最終的にスキャンして仕上げます。そしてこの原画を途中で提出したら、吉村さんが「これを展示しましょう」と言って、まんまと展示してくれました(笑)。

吉村:展示の内側に入ると原画が見られるのですが、外側からはその制作の痕跡が見える。だから裏も見てほしいという展示です。また、これ(と、展示されている1枚を指差す)は漫画のすべてが描かれていない。でも壁際に展示している完成した漫画を見ると、すべて描かれている。それはコピペによってなんですよね?
座二郎:そうです。漫画を見て、一部コピペだというのは多分わからないと思う。バーティポートの巨大化されたものが見開きいっぱいに広がっているんですけど、全部描くのは大変なので(笑)、6割くらい描いて、残りはコピペしても分からないだろうと思って、部分的に描いている状態が展示されています。完成したものと見比べると面白いんじゃないかな。
吉村:そういう裏技的なことは他にもやっているんですか?
座二郎:よく見ると、描き損じというか、ちょっと汚くなってしまったものはデジタルで修正しています。そのほうが早いので。
吉村:ここに展示している原画には「吹き出し」にまだ台詞が入っていないのもおもしろいと思います。
座二郎:原画を展示するための台紙として、いろいろな紙が使われていることにも注目してください。
吉村: そしてこの壁(中庭の反対側の壁)に展示しているのは「漫画建築史年表」です。上段の建築史では、漫画や絵画、出版に影響を与えたのではないかと思う建築での出来事、下段の漫画史では、建築に影響を与えたのではないかと思う漫画や絵画、出版での出来事を取り上げています。例えば1400年代にブルネレスキが線遠近法(透視図法)の方法論を生み出し、その少し後にグーテンベルクが活版印刷を発明したことで銅版画の印刷への道が開け、1700年代にピラネージが古代ローマの都市景観を細密なエッチング技法で描いた、というように、上下を対比させると、これとこれはもしかしたら関係しているのかも、というのが見えてくる。この年表は早稲田大学の僕の研究室が本展のために作成しました。
中庭への出入口の手前の本棚には、漫画に関係する書籍を自宅から持ってきて並べています。
座二郎:今回の展示に関わった漫画家の本がひと通り置いてありますね。依頼を断られた人のも。
吉村:漫画家には結構断られたんです。打率3割といったところでした。
(中庭に移動)
吉村:スケールフィギュアって分かりますか?建築家が描くドローイングやパース、図面などに人間を入れることでスケールを把握しやすくするものです。それを1/1に拡大して展示しています。僕が学生時代のものもあります。スケールフィギュアは建築が完成したら要らなくなるものなので、フィクションとして世の中に存在するという意味で、漫画とどこか近しい感じがして展示しました。
座二郎:スケールフィギュアは身長170cmくらいに拡大されているんですよね。
(4階に移動)
吉村:展示の平面計画は下の階(3階)と同じで、下の階では漫画を通して見せていた僕の作品を、この階では模型と図面で見せています。建築展では珍しいと思うのですが、写真は一切ありません。1番から6番の建築は完成しているけれど、7番の「VERTIPORT(バーティポート)」はまだ建っていないので、その差をなるべく小さくするために、図面に写真を入れませんでした。
座二郎:今気づいたんですけど、中央の展示は絶妙なコマ割りですね。外周から全ての模型を見ることができる。そういうコマ割りにしていることがこの階に来て改めてわかりました。普通に割ったら、外周に接しないコマが出てきちゃうものですけど、これはそれがないようにちゃんと調整されている。
それと、これは私の勝手な解釈ですけど、下の階では漫画で表現されていた建築が、現実世界のものとして上の階に飛び出していて、上下の階に共通するコマ割りの線は敷地境界線のようなもので、すごく建築の展示だという感じがします。
吉村:1番は下の階と同じく「Nowhere but Sajima」。2006年頃から設計を始めて2008年に竣工した住宅です。1週間単位で家を貸すサービスを提供するNowhere resortという会社を立ち上げ、葉山に続く2軒目として建てたもので、今のような民泊制度ができる前のことです。この住宅は海に面して窓をたくさん設けて眺望を開きつつ、周辺からの視線を遮ってプライバシーを確保するということを両立させるために、細いトンネル状の窓を開けました。中にいる人は立つ位置で眺望とプライバシーを自らコントロールできます。
2番の「Red Light Yokohama」については下の階で説明した通りです。
3番の「窓の家」は、「Nowhere but Sajima」に泊まった人からの依頼で建てたものです。海に面した敷地は3m×8mの大きさしかない。また、建てることで背後の山側に立つ家の海への眺望を遮ることになる。そこで、海側と山側に同じ大きさの窓を開け、2枚のガラス越しではあるけれど、背後の家の人も以前と同じように海への眺望を楽しめるという家を設計しました。
4番の「フクマスベース」は既製品のテント倉庫を転用した子育て支援施設です。
座二郎:この模型にはテントがないけれど、実際は外側にテントが張ってあり、その中に屋根のない建物があるんですよね。私は吉村さんのこの建築に多大な影響を受けて自分の家を設計して、結果的に屋根のない家が出来上がりました。
吉村:5番の「ホームトゥーゴー#001」は、シェアハウスを2軒所有する4人家族のクライアントから、その2軒の間を行ったり来たりしながら暮らせる家を設計してほしいという依頼があり、このキャンピングカーのようなものが出来ました。内部は平面が1400×2000mmのダブルベッドと同じ大きさでまるで二段ベッドのようです。
6番の「滝ヶ原チキンビレジ」は先ほど話したように鶏舎です。大学の研究室の学生を対象に設計コンペを行い、自力建設することにしました。興味があるのが2案残り、選べなかったので、2つともつくっていいというお許しをいただき、「個室群鶏舎」と「傾斜鶏舎」があります。鳥は爪が伸びるけれど、土の上で暮らしていれば研がなくていいので、どちらも1階の床部分は土にしました。
7番の空飛ぶクルマの空港「VERTIPORT(バーティポート)」はコンテナでつくる計画です。大きさは約100㎡しかないけれど、ここは管理棟、あちらはラウンジと、空港の機能はすべて満たしています。40フィートコンテナの長手を5分割すると、コンテナの短手の長さ8フィートとぴったり合うので、それを1単位としたユニット形式にしています。
座二郎:これは実際に建設予定なんですよね?
吉村:東京のお台場に建てる予定だったのが、商業利用はできないと言われてしまい、今は三重県に場所を移して計画が進んでいます。
奥の壁でお見せするのは、20世紀以降の「半動産建築」を集めた年表です。半動産は可動産と不動産の間という意味を持たせた造語で、それを「止まらない家」「ずっとはない家」「大きくない家」というふうに「〜ない」という10のカテゴリーで分類しました。
その横の壁では「技術史」と「建築史」を対比させた年表を展示しています。この技術が発明されたからこの建築ができたというだけではなく、この建築ができたからこの技術が生まれたという逆もあると見ながら線を引いて結びつけています。この年表は建築学会の建築雑誌で一度発表したことがあります。
最後に、この階の窓側の本棚には、僕が脳出血を発症して、病気と空間の関係を考えるようになって選んだ本のほかに、2010年にこのTOTOギャラリー・間で行われた「建築家の読書術」というイベントで選んだ20冊のうちの10冊の本を並べています。15年前、僕は30代だったわけですが、なかなかいい選書をしているじゃないか、と思ったので。ぜひ手に取ってご覧になってください。
(クロストークへ続く)

中山:吉村さんとは同い年で、20代からのお付き合いです。ずっとまぶしく見ている友人でありライバルですが、僕の世代でその文章や言葉に感化されたことのない人はきっといなくて、自分の中ではロゴス(理論)の人と思っています。
口火を切る役ということで、ちょっと長く話していいですか?

一同:(笑)
中山:展覧会のタイトルに掲げられた「建築家の不在」が、やはり今日の主題の一つですよね。では、そもそも建築家って何なのでしょう。いろいろ見方はあると思いますが、その始まりとしてよく挙がるのがアンドレア・パラディオ(1508-1580)です。ルネサンスの人だから、たかだか500年くらい前の話ですね。この時代に生まれたのは、世界の森羅万象にはその上位に、抽象的な概念の世界があるのではないか、といった考え方です。つまり建築もまた、その上位に理想的な比例や幾何学の世界がある、と。実際に現場というのは図面やコンセプトの通りにはいかないものですが、本質はそれらを記した書物の中にあるのであって、つまり署名入りの記述こそが建築なのだ。乱暴にいってしまえば、パラディオはそういうスタイルを打ち出した先駆者でした。建築を作品として建築家名で発表するスタイルは今に至るまで続いていて、だから恥ずかしながら自分も、この500年来の流行の末端にいるわけです。
ただ、この建築家なる存在への懐疑は、歴史を遡ると幾度となく試みられています。有名なのは、1964年にMoMA(ニューヨーク近代美術館)で開催された、バーナード・ルドフスキー(アメリカの建築家・著述家)の有名な著作名にもなっている「建築家なしの建築(Architecture Without Architects)」展ですね。これは無名のヴァナキュラー建築への再注目で、日本における民藝運動とも近いかもしれません。
時代は飛びますが、その後の日本で思い出されるのが、1990年代の終わりにみかんぐみの曽我部昌史さんが発表した「非作家性の時代に」(『新建築住宅特集』1998年3月号)という論考が巻き起こした議論です。これは、建築をめぐる多様な価値判断を、複数メンバーの合議制によるフラットな評価軸で下してゆく姿勢をステイトメントしたものでした。個人名を冠したアトリエ系事務所と区別して、「ユニット派」といった呼称もありましたよね。
それで、いよいよ吉村さんです。最初の設計事務所の名前は「SUPER-OS」でしたよね。立ち上げは何年でしたっけ?
吉村:2001年です。
中山:「SUPER-OS」も弟の英孝さんらを含むユニットでしたが、ここでいよいよ到来するのがインターネットです。OSはコンピュータのオペレーションシステムのことですよね。僕の見立ては、このとき吉村さんが意識されていたのは「Linux」のようなイメージだったのではないか、と。ヘルシンキ大学の学生だったリーナス・トーバルズが、自作OSのソースコードをウェブ上に全公開したのは1991年です。これは次世代OSの寡占を競い合うビジネスモデルへの批判でもあったし、なによりも世界中のエンジニアたちがコーディングに参加したりカスタマイズしたりできる、今でいうクリエイティブ・コモンズや集合知といった議論の先駆けだった。だから、吉村さんがチーム型の設計事務所に「SUPER-OS」と名づけたとき、新しい社会の到来への素早い反応だと内心驚いていました。このような議論の決定的な著作の一つであるローレンス・レッシグ(アメリカの法学者)の『コモンズ:ネット上の所有権強化は技術革新を殺す』(翔泳社)が日本語訳されたのは2002年ですから。
一人で長々話してしまって申し訳ないのですが、初めにこんな振り返りを思いついたのは、今回の図録に収録されている年表がとても興味深かったからです。例えば「建築家なしの建築」展が開催された1964年前後を見ると、ロイ・リキテンシュタインが出てくる。ポップアートを代表する作家ですが、ポップアートの特徴に作家性の否定がありますよね。
それからLinuxが登場した2000年前後を見ると、村上隆さんによるスーパーフラット宣言が挙げられている。これはひと言でいうと、作家による一義的な価値判断への批評ですね。世界の多義性を記述するためには、作家自身が徹底的にフラットでなければならない、というこのスタンスは、みかんぐみの「非作家性の時代に」での議論と重なっているところがある。
そしてこの展覧会です。「建築家の不在」には、自身の展覧会のメインコンテンツを他者に委ねることと、そのスタンスがローレンス・レッシグ的、あるいはリーナス・トーバルズ的社会背景への鋭い応答であることの、二つの意味が重ねられているのだと感じましたが、どうでしょう?

吉村:今回は漫画家ですが、僕はこれまでも他者を呼んで展覧会をやったことがあります。例えば2010年に開催した「CCハウス」展。CCはクリエイティブ・コモンズのことで、建築では長く著作権が認められてこなかったけれど、その問題を前進させる手掛かりとして建築のCCを考えるにあたり、この展覧会では周りのグラフィックデザイナーやインテリアデザイナーなどにCCハウスの変形を頼み、それを展示しました。また、「Re:Public」と題して2013年に豊田市美術館で開催した個展では、模型を1/6のスケールで展示しました。
座二郎:1/6とは大きい。それに中途半端ですね。
吉村:そう、中途半端なんだけど、ヴィトラデザインミュージアムの名作椅子のミニチュアコレクションがオリジナルの1/6だったので、それに合わせて、すごく巨大な模型を作ったんです。展示物を置く展示台は発泡スチロールの原反を利用していて、その原反の大きさ1m×0.5m×2mは、僕が設計したコンテナ2段積みの「ベイサイドマリーナホテル横浜」(2019年)の1/5に近い。つまり、展示台として使われる発泡スチロールはベイサイドマリーナホテル横浜の模型にもなっている。ほかの3つの作品の模型も1/6で作って展示しました。
中山:吉村さんはずいぶん早くからコンテナにも注目していますよね。マルク・レビンソン(アメリカの経済学者)の『コンテナ物語(THE BOX)』(2007年、日経BP)というベストセラーがありました。コンテナの発明以降、1000人の沖仲仕が半日かけて積み込みを行っていた量を、オペレーター3人が30分で終えてしまう時代になった。コンテナの世界規格化が、今日の生産と消費の分離を爆発的に推し進めたわけです。吉村さんの著書に『ビヘイヴィアとプロトコル』(2012年、LIXIL出版)がありますね。プロトコルはコンピュータ用語で、通信のための共有言語のこと。
ヴィトラの縮尺に合わせた模型だとか発泡スチロールの原反のモジュール、そしてコンテナ。吉村さんはそうした社会化された規格としてのプロトコルに対して、その共有言語の中に忍び込んで、まるで他人を勝手に喋らせるかのようにいつの間にか建築化してしまう。そんな感覚は吉村さんの中で、いつどこで育まれたのでしょうか。オランダに行かれたのが大きかったのでしょうか?
吉村:僕が在籍したMVRDVの事務所はオランダのロッテルダムにあり、事務所の隣にマース川が流れ、コンテナ船が日々行き交っていました。そのコンテナ船をボーッと眺めて、コンテナで何かできないかな、ということは思っていましたね。でも、小学生くらいのときから、そういう可能性を考えていたように思います。
中山:効率がいいものが好きなんですかね?
吉村:なんだろうね。僕は豊田市で生まれ育ったんです。父が自動車のエンジニアで、トヨタの車をなんとかするために車のデザイナーになりたいと思い、デザイナーの経歴を調べたら建築学科を出た人がいたから建築の道に進みました。今、車のデザインはできていないけれど、軽トラの荷台に載るものはデザインしているから、効率がいいものが好きというところはあるかもしれません。
中山:量産品への興味が強いってこと?
吉村:ある、ある。あると思うなあ。
中山:なのに量産品ではない建築を選んだ(笑)。特に建築家と呼ばれる人たちが設計したものは。
座二郎:吉村さんが狙うのは建築と量産品の間みたいなところですよね。今回展示された作品では「フクマスベース」もそうだし。4階には吉村さんの作家性と言っていいのかわからないけど、吉村さんはこういう建築家だとわかるものはどちらかというと4階に集まっていて、私は3階の人なので、少しは3階の話もしないと帰れない(笑)。
吉村:そうだね(笑)。
座二郎:先ほどの中山さんの話から、建築家の作家性を問うということで言うと、60年代、90年代、今は2025年だから、ちょうど30年ごとにその波が来ているんじゃないかという気がします。一方、漫画の世界では今のところ、漫画家が作家性を捨てて漫画を描くなんて議論は起きていない。歴史を詳しくひもとけばもしかしたらあったのかもしれないけれど、少なくとも私の目には入ってきていない。
今回の展示は作家が7人集まって、吉村さんの作品をなんかしようというものなんですよね。私は一応建築学科を卒業して建築家を名乗っていて、その立場で漫画を描くからには現代の建築家が置かれている状況みたいなものを描きたいと思いました。蓋を開けてみるとそういうアプローチの人は川勝徳重さんと私だけで、ほかの人たちはわりと真面目に建築を捉えていたかなと思います。どれもいいところがあって、それぞれ1時間ずつしゃべれるんですけど(笑)、それは置いておいて、川勝さんの漫画は「建築家とは」ということをすごく突いてきた感じがありました。建築家がすごく意地悪に描かれていて、目を覚まさせるというか。本人は打ち上げで「いやあ、吉村さんが可哀想だよ」と語っていましたけど、自分で描いておいて(笑)。
中山:横浜黄金町が舞台の「Red Light Yokohama」ですね。
吉村:わからず屋の建築家として僕のことが描かれている(苦笑)。
「Nowhere but Sajima」にそっくりな建物が台湾にある
中山:座二郎さんは「建築家の不在」というお題をもらってから、吉村さんのどの作品を選び、なぜ空港をテーマにしたのですか? 『ガリバー旅行記』みたいなストーリーですよね。

座二郎:ストーリーは中山さんがおっしゃる通りです。吉村さんの作品のどれを選ぶかについては、私は自宅を設計するときに影響を受けた「フクマスベース」を選びたかったんですが、選択権は漫画家側になく、「君はこれ」と言われて「VERTIPORT(バーティポート)」を扱うことになりました。それで私は、コンテナを使ったシステムみたいなものと、いろんな場所で同じモノが再現される空港というものと、たぶん最初は「建築家の不在」というテーマは言われていなかったんですけど、今の建築家の置かれている状況みたいなものを批評的に表現したいと思ったときに、『ガリバー旅行記』がモチーフとして思い浮かんだんです。『ガリバー旅行記』はご存知のように、ガリバーがいろんな国を巡る中で当時のイギリスの世相を風刺する話なので、私も今の建築家の置かれている世界を思いっきり批評してやろうと思って、エッジを効かせて描いたんですけど、エッジという意味では川勝くんにちょっと負けたかなという気がしています。
中山:どういう批評なのか、もう少し具体的に聞きたいな。
座二郎:単なるストーリーの説明になっちゃうんですけど、まず基本的なプロット(話の筋)を、空飛ぶクルマに乗って旅する人たちが、建築家のいなくなった世界で建築家が設計した空港を探すというものに設定しています。「建築家の不在」というテーマは確か聞かずにこのような設定を考えたのは、今の状況がなんか探している感、不在感があったからです。
『ガリバー旅行記』には頭が良くて理性的な人たちが馬の形をして出てきます。私の漫画では馬の形をした人たちが天空に浮かぶ空港に住んでいて、「この空港は最初に、ガハ・ザーディドという建築家が設計者に選ばれたけれど、予算の問題などで外された」と話す。新国立競技場の設計過程においてザハ・ハディドの原案が白紙撤回された出来事は、私は非常に大きな事件だと思っているので話の中に盛り込みました。ガハ・ザーディドという名前はすごく気に入っています(笑)。
中山:座二郎さんは、作家としての建築家に憧れがあるように聞こえますね。
座二郎:めちゃくちゃあります。私が建築学生だった1995年頃に戻っちゃうんですけど、あの頃に憧れていたスタイルの建築家は、今はもういないような気がしています。少なくとも私には、いないように見える。
中山:新国立競技場の一連の出来事は、日本において建築家なる存在がいよいよいなくなっていく、その象徴的な出来事として感じたというわけですね。でも座二郎さんの漫画には「建築家とは専門家の名前を借りて建物を利己的に設計するいやしい職業」とも書いてあって、これはルドフスキーの本からの引用だといわれても、すんなり納得してしまう。(一同笑)いや、座二郎さんがいいたいことはよくわかります。僕自身、そう思うことがたくさんありますから。
今日の冒頭のお話は、建築史家で東京大学教授の加藤耕一さんの著書『時がつくる建築:リノベーションの西洋建築史』(2017年、東京大学出版会)からの影響が大きいのですが、この本では例えば、パリにあるフランス国立図書館の閲覧室を、アンリ・ラブルーストによる19世紀のスティール表現という“点の建築史”として理解することを批判しています。エティエンヌ・ルイ・ブーレーの有名な閲覧席のドローイングが、18世紀に同じ場所に計画されたものであることを挙げながら、どちらの建築家も既存建築物の様子を注意深く読み解きながら、計画はいつもそこへの応答としてあることを指摘しています。そうした様子をつぶさに見ていくと、点の建築史ではなく、連続的なリノベーションとしての“線の建築史”が見えてくる。そんなお話です。
吉村さんはさっき、量産品というものに対するある種の感情が原体験としてあるといっていましたよね。同時に、ある考え方が世の中に示された瞬間、それ以降の世界が変化していく、いってみれば点から始まったものが線として広がっていくという状況のようなものに対する興味も、一種の「建築家の不在」といえるかもしれません。吉村さんの「CCハウス」は、建築家が設計ツールを配って、iPadで誰もが自由に組み合わせを考えながら建築を作っていくことができるというものだった。プロトコルが公開されたツールが勝手にカスタマイズされながら、建築家の意志を超えて広がっていくイメージは、リノベーションとは違いますが、これも一つの線的な建築活動だったのではないかと思います。
また、座二郎さんから先ほど、漫画家は作家性を捨てられないという話がありましたが、例えばコミックマーケットという今や日本最大のインディペンデントなイベントは、いってみれば巨大な二次創作祭りですよね。僕は残念にも漫画を読む習慣がないので実情はわからないんですけど、今や作品側に二次創作を想定したキャラクター設定を確信犯的に埋め込んでおくようなことも、あったりするのではなんて思ったりします。
二次創作を嫌がる作家も当然いるでしょうけれども、もしもニヤリとするタイプの作家もいたりするなら、吉村さんは後者ですよね(笑)。
吉村:「Nowhere but Sajima」と同じような建物が台湾に建っているんですよ。あの感じで小さい窓がたくさん開いていて、それを2回繰り返しているから立面は縦長なんだけど、これは貴方が設計したんですか? と台湾の人から問い合わせがあって知りました。でも僕は訴えようなんてことは全く思わなくて、逆になんかニヤリとしちゃいましたね。
座二郎:私の自宅は吉村さんの「フクマスベース」の二次創作です。完全にフクマスベースの影響から作りました。最初は既製品のガラスの温室みたいなものの中に、フクマスベース的に屋根のない家を建てようとしていたんですけど、建蔽率の問題があったので、屋根がない部分を作る方向に変わっていったという流れで、そのことは当時から吉村さんに伝えていました。
中山:でも、座二郎さんの家は二次創作ではないんじゃないかな。台湾で建てられたようなものとは違う。
座二郎:まあ、そうですね。私の家は、いわれないと気がつかないでしょうからね。
中山:そもそも多くの建築家が自作を語る中には、そこにある開かれた言語性のようなものへの意識というのは必ずあって、その一つの例証として建物を作っているような、つまりパラディオ的な建築家のあり方の中にも、実は今日の「建築家の不在」にまつわる議論への接点はあるんですよね。90年代終わりから2000年代初頭のオランダ、ちょうど吉村さんがMVRDVに行かれた頃には、例えば「データスケープ」といった造語を使って、あたかもリサーチや統計が直接出力されたかのような建築形態で、その後の建築表現に決定的な影響を与えました。このスーパーフラット的ともいえるようなスタンスは、みかんぐみもそうだったと思いますし、吉村さんや僕を含む後の世代に影響を受けなかった人はいないのではないか。吉村さんのフクマスベースと座二郎さんがご自宅で考えられたこととも、こうした建築家個人を超えた言語性の継承というか、そういう関係に近いものを感じます。
座二郎さんのご自宅は皆さんご存知ですか? 僕は遊びに行ったことがあります。平面がロの字の家なんですよね。延床面積は何平米でしたっけ?
座二郎:吉村さんの展覧会で私の家の説明をするのは恥ずかしいのですが、60平米しかなくて、リビングの空間に屋根を架けないことで建蔽率と容積率を逃げているという家です。
中山:なんて淡白な説明。(一堂笑)僕が少し補足すると、家の真ん中で空が見えるんです。サッシが中庭をぐるりと囲んでいて、居住スペースがロの字形になっている。ただ、2階ではL字形にベランダになっている2辺は奥行きが薄いので、1階では中庭からアクセスする収納になっている。例えばリビングから中庭越しに、サッシのガラスを2枚挟んで反対側の収納に入っているテレビを見るようなことが起こっているんです。この露天の中庭で建蔽率を回避しているわけだけど、テントを掛けると部屋みたいになるんです。僕が行ったときにはテントを開けてくれて、家の真ん中に空が現れてびっくりしました。
座二郎:そうそう、それでシャンパンの蓋をばーんと飛ばしてね(笑)。
中山:フクマスベースができた過程もおもしろいですよね。最初は鉄骨造の大きな既存の倉庫をそのまま使って、その中にジャイアントファニチャーのような木造構造体を置く案だったんですよね。でも最終的には既製品のテント膜倉庫を新規に設置する構想に変わった。あれは法規制の関係からだったの?
吉村:目の前の道路に近く建ちすぎていたからね。
中山:そうだったんですね。ただインフィルとして計画していた、漫画にも描かれていたオリジナルの自在ジョイントで補強した衝立のような構造物は、最初の案のときに既にある程度開発が進んでいたんですよね。それでなんと、元あった倉庫と同じプロポーションの上屋をテントで作り直すという、見方によっては自作自演的なことをしている。ただ、経緯はどうあれ、ここで示されたことには、座二郎さんを含むその後の思考や、汎用的な金物の開発といったプロトコル的思考が通底しています。つまりこのプロトコルは世界中の納屋に新しいビヘイヴィアを示す。

座二郎:漫画では三池画丈さんがフクマスベースを描いていて、三池さんの漫画も別の形のアンサーだったと思うんですけど、三池さんの漫画はすごく優等生的というか、漫画家に頼んでこういうのを描いてくれたら一番嬉しいよねというものだったと思います。フクマスベースの建築を外皮と中身に分け、擬態生物として宙に浮かんでいた中身を外皮の中に追い込んだ結果として今のフクマスベースがあるというストーリーで、非常に分かりやすくて、採点すればエープラス(A+)みたいな。
実際に建つことがそんなに大事だとは思っていない
中山:吉村さんは第三者によって自分の建築がまったく別の二次創作物となっていく様子を眺めていて、どんなことを思っていたのですか?
吉村:想像しているものとは違うものが毎回出てくるから、おもしろかったですね。今回は漫画家のクリエイティビティに全面的に頼っているところが、「CCハウス」展など今までの展覧会と違う点だと思っています。CCハウス展ではグラフィックデザイナーやインテリアデザイナーに変形を頼んだけれど、その模型は僕たちの事務所で作ったので、そこで一度調整して展示した。今回は全く調整できないものがボンと出てきて、それを展示しているからね。
中山:ただ、ここまでいっておきながら吉村さんの今回の展覧会が、ではほかの建築家の作品やその発表の方法に適用できるのかと考えると、実は結構難しいんじゃないかとも思っています。やっぱり吉村さんの仕事がもっているある種のオープンソース性が、他者による創作へのジャンルを超えたプロトコルとなる。このことはすごく重要だと思います。
吉村:僕は建築設計を通して開発したものを囲い込む気は全然ないんですね。一般に広がればいいなと思ってやっているんだけど、なかなか広がらないだけで(笑)。
中山:Nowhereシリーズの仕組みも時代を先取りしていましたね。自分自身が建主となって家を建てて、それを貸し出す。今でこそ「NOT A HOTEL」をはじめ、個人で別荘を所有することとはまた違う試みがビジネスとしても注目されているけれど、Nowhereシリーズを吉村さんが始めたのは20年前ですからね。時代がようやく追い付いたともいえる。
座二郎:ちょっと話を変えますけど、私は建築と漫画の間に暮らしていて、今回の展示を見てすごく思ったのは、漫画家の成果品はこれ(本)なんですよね、これしかない。漫画家はこれを目指して一所懸命に手を動かして図面っぽいものを描いているんですけど、建築家は最終的な成果品が図面でもなければ、その図面をもとに作った建築でもない。もっとその先にあるものを見ているんだと最近思い始めていて、それはもしかしたら、中山さんが冒頭に話した本に記述できるものという話でもあるのかもしれないけれど、今回の展示は、そこに対するものが何か見えそうな気がしています。例えば漫画が拡大されているのはすごくおもしろくて、我々漫画家は図録の大きさ(A5判変型)に仕上がることを目指して描いているわけだけど、それが拡大されたり模型になったりして、なんだか建築に近づこうとしているように見えるのが私にとってはおもしろかったんですよね。だから漫画系の人にも今回の展示を見てほしいけど、漫画家ってそもそも外に出ないし、展覧会を見に行く習慣もあんまりないんですよね。あと文化として、建築系の人は展示よりも建築の実物を見に行くほうがいいと思うじゃないですか。漫画家は本を見れば、最終成果品を見たことになりますからね。
中山:僕は現実の建築を見に行くのは、実はそこまで好きじゃないんですよ。
座二郎:そうなんですか(笑)。でも実物を見ないで批判している人がいたら、ちょっとイラっとしたりしませんか?
中山:全然ないんです。
座二郎:建築の実物を見に行くことに興味がなくて、資料で確認することが正しいと思っているということですか?
中山:パラディオの話に戻るかもしれませんが、僕が初めに取り憑かれたのは、文章と写真と、あとその模型や図面の組み合わせで、建築家がその思想を記述することへの憧れだったんですよね。学生時代の長期休暇も、周りの友人たちが海外に旅立つ様子を横目で見ながら、僕はずっと図書館に籠もって、新建築の合本を積み上げて、今日はここからここまでと決めてページをめくるような日々を送っていたので、だからいまだに実際の建築を見に行ってもどういう感想を述べていいのかわからなくてまごまごすることがよくあるんです。そんなだから、建築の写真を撮るのもすごく下手なんです(苦笑)。最初に吉村さんをロゴスの人といいましたが、吉村さんは自分で写真も撮りますよね。
吉村:でも僕はそんなに写真は上手くないから。撮っているだけだからね。
中山:そんなことはないですよ。
座二郎:今回の展示では写真が1枚もないって、私は途中まで気づかなかったんですけど、写真に対するなんかこだわりがあったんですか?
吉村:ないほうがいいと思いましたね。
中山:どうして?
吉村:実際に建つということがそんなに大事だとは思っていないんです。それと今回の7つの中にはまだ建っていないものもあり、建っていない建築と建っている建築の差をなるべくなくしたいという思いもありました。
中山:それを聞くと納得です。僕は吉村さんにも、建築をあちこち見て回っているという印象はそこまでないかもしれない。
吉村:え? そうかな、僕は見ていると思うけど。でも、中山くんが建築を見ないで建築を楽しむ方法があるというのはその通りだなと思う。
中山:年表にもスーパースタジオが挙げられていますが、60年代に彼らやアーキグラムなどが、自分たちの考える建築世界を漫画に近い表現で提示した時代がありましたよね。図面化できない出来事としての建築を表現するのに、漫画的な手法はとても有効でした。今日の議論でペーパーアーキテクトと呼称される建築家像について触れないわけにはいかないですが、例えば思い出すのはセドリック・プライスのファン・パレスの計画です。これは組み立て式モジュールとクレーンを使った可動式建築で、ご存じのとおりアンビルトですが、ドローイングが非常に素晴らしい。気づいていない人が多いけれど、実は奥に火力発電所の煙突が見切れていて、これは要するに電力が都市に安定供給される時代になると、それまでは煉瓦でつくられていた建物が動き出して、出来事を建築が追尾し続けることができるようになる、という。発電所とともに森が描かれているのも示唆に富んでいますが、よく見ると空にヘリコプターが飛んでいて、次のドローイングは操縦席からの鳥瞰図なんですよね。これもどこかコミックの手法に近い表現ですが、ルネサンス的な比例と理想的人体だけではない、人類史の新しい展開を建築における漫画的表現は拓いてみせた。吉村展もそうした系譜のエッジに置かれるべきものだと思います。
――話は尽きませんが、そろそろ時間ですので、最後にひと言ずつお願いします。
座二郎:よく考えたら、私の家の吉村的な部分は屋根の有無ではなくて、半合法なところかもしれませんね。
中山:あ、その話を今日はしなかったね。
座二郎:私の家は本来なら屋根を架けるところにタープを掛けている。吉村さんは『超合法建築図鑑』(2006年、彰国社)という本を出していて、超合法とは違法や脱法の対義語として名付けたものですよね。吉村さんは半動産もそうですけど、建築と建築じゃないものの間、あるいは合法と合法じゃないものの間みたいなところをすごく突いてくる人で、今回の展示で漫画と図面の間を突くということに関われたのはすごくいい経験だったというのが私の感想です。
中山:最初に話題にしたレッシグには『CODE:インターネットの合法・違法・プライバシー』(2001年、翔泳社)という本もあって、コード、つまり法規とは、突き詰めれば自分たちは何者であるかへの定義の試みです。一義的な定義は私たちを縛る檻になりますが、同時に開かれたコードはプロトコルとなって、豊かなビヘイヴィアを生み出しもする。最後にうまくまとまりましたね。
もうちょっとだけ膨らませられると良かったのは、量産品に対する吉村さんの愛情みたいなもの。それはこの後、お茶でも飲みながら話の続きができたらなと思います。
吉村:今日は二人にやたら褒められて、居心地が悪くてしょうがなかったんだけど(笑)、脳出血になって、褒められているのも貶されているのも客観的に聞けるようになったんです。だからこういう会が時々開かれるようになるといいなと思っています。皆さん、ありがとうございました。

https://bunganet.tokyo/


画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。