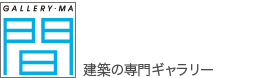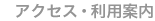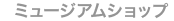- 展覧会TOTOギャラリー・間
- これからの展覧会
- 過去の展覧会
- 展覧会レポート
- 展覧会他会場
- これからの展覧会
- 講演会
- これからの講演会
- 公開中の講演会
- 過去の講演会
- 講演会レポート
- アクセス・利用案内・団体利用案内
- アクセス
- 利用案内
- 団体利用案内
- ミュージアムショップ
- Bookshop TOTO
- スマホ画像ダウンロード
建築文化活動
TOTOギャラリー・間
TOTO出版
Bookshop TOTO

展覧会レポート
終わりのない建築を目指して
レポーター=津川恵理
展覧会に入ると、まずは巨大なニワトリが出迎えてくれた。そんな建築家の展覧会は、後にも先にも無いだろう。
展覧会に入ると、まずは巨大なニワトリが出迎えてくれた。そんな建築家の展覧会は、後にも先にも無いだろう。
これは、漫画家のメグマイルランド氏が吉村靖孝氏の「滝ケ原チキンビレッジ」を描いた漫画の中に出てくるキャラクターらしい。が、これを建築家の展覧会としてどう受け取れば良いのか、初めは戸惑いがあった。
吉村氏は2010年、建築図面の一部の著作権を放棄する「CCハウス」を発表した。2階建ての2棟の住宅が、1つの階段室でつながるプロトタイプから始まり、設計者としての著作権を一部放棄することで、どのような敷地にも変転可能なシステムになっている。これは、建築家が描いた図面を販売し一部改変可能とすることで、音楽でいうリミックスやサンプリングなどに見られる表現手法のように、オリジナルから派生してどんどんアレンジされた設計が広がっていく提案である。
また、2014年に発表した「アプリの家」では、ユーザーが木造住宅の設計から発注まで行えるアプリケーションの開発を行っている。窓の位置や収納位置を自由にカスタマイズできるよう、一般的なモジュール工法よりも小さな1,200mm単位で立面を構成し、建築設計を民主化するためのシステムを設計している。
これらの活動から読み取れるのは、建築家が設計する建築はいつも一点もので、竣工した瞬間に終わりを迎えてしまう喪失感への抵抗なのではないだろうか。プロダクトデザインやファッションデザイン、映画や音楽は、いつも製作された後に市場へと広がり、多くの人の生活や体験に接していく。しかし建築は、公共性の高い建築でない限り、竣工後の内部を体験することはできない。また、その場に行かなければ体験できず、市場に出回る他分野の創造とは明らかに違う。「CCハウス」や「アプリの家」からは、“建築をオープンエンドにする”というメッセージが聞こえてくるかのようだ。
その上で、本展覧会を見てみよう。
既に竣工した6つの建築と、現在進行中の1つの建築を題材にし、7名の漫画家が吉村氏の設計した建築を題材に自由に漫画を描いている。漫画家の選定と、どの建築を誰に描いてもらうのか、その組み合わせは吉村氏自身が決めたらしい。重力もなく、時間すらも自由に操れる漫画の世界で、建築が縦横無尽に解体されていく。
次に、これらの漫画を受け取り、吉村氏が新たなメディアとしての建築を構築する。それらは不可思議な模型だったり、小さなインスタレーションだったり、時間がずれて投影される映像だったりする。漫画家との往復書簡により、建築にまつわるメディアに広がりが生まれる。漫画という媒体を通すことで、設計された建築がリミックスされ、サンプリングされ、再編されて新たな創造物としてアウトプットされている。それらを3階(GALLERY 1)の中央部に展示し、建築の創造物としての実験を行っているような展示だった。“建築をオープンエンドにする”試みを行ってきた吉村氏だからこそ生まれた、建築の終わりなき創造性への挑戦だったのだろう。
4階(GALLERY 2)では、3階に展示されていた7つの漫画と対応するように、3階と同じレイアウトで7つの建築の図面と模型が展示されている。ここで1つ気がつくのが、建築の展示によくある敷地模型と竣工写真が一切無いことである。周辺のコンテクストや、完成したイメージの情報を排除することで、TOTOギャラリー・間に展示される7つの建築が独立した文脈として走り出す。漫画という、異分野のメディアを通して出てくる独自のイメージが膨らんでいく様を、情報を絞ることで際立たせていた。

GALLERY 1(3階)奥に漫画作品、中央に漫画から着想を得た展示品が並ぶ。© Nacása & Partners Inc.

GALLERY 2(4階)奥に図面、中央に模型が下階と同じレイアウトで並ぶ。© Nacása & Partners Inc.
この展示手法は、吉村氏が唱えていた“ポストファブリケーション”や、“アドホック”とも似ているのかもしれない。TOTOギャラリー・間を敷地と捉えてみると、その場でつくられる建築の事後の創造性、また鑑賞者の想像がそこに絡むことで、社会に実際に建った建築とはまた違う像が浮かび上がる。図面や模型などによって一度建築がスタティックな状態になった「あと」、そこに建築家がどう関われるかを模索しているように感じた。
今回の展覧会レポートは、建築家として私が大切にしているある種の作家性に重ね合わせて見たものである。それは、(1)建築の事後の状態を設計すること、(2)建築の新しいメディアの可能性を模索すること、(3)偶発性に身を委ねて設計してみること、などである。
本展は2年前に吉村靖孝氏が脳出血を患ったことから物語が始まるのだが、総じて抱いた感覚は、吉村氏の脳はまだまだ生きている、と実感したことである。今までの活動の延長にありつつも、まだ新たな創造の先を行こうとする活力は死んではいない。52歳を迎えたということだが、社会情勢が不安定なこの時代を乗りこなす建築家として、今後はどのようなアプローチを仕掛けてくれるのだろうか。同じ建築家として、私自身も鼓舞される展示だった。
津川恵理
建築家/ALTEMY代表。2015年早稲田大学創造理工学術院建築学修了。2015~2018年組織設計事務所勤務。2018年より文化庁新進芸術家海外研修員としてDiller Scofidio+ Renfro (New York)勤務。神戸市主催「さんきたアモーレ広場デザインコンペ」最優秀賞受賞をきっかけに帰国し、ALTEMY設立。
主な作品に、「サンキタ広場」(2021)、「Spectra-Pass」(2021)、「まちの保育園 南青山」(2024)、「庭と織物――The Shades of Shadows <織物共同開発/空間構成>」(2024)などがある。2024年に「渋谷公園通りデザインコンペ2040」で最優秀賞を受賞した他、国土交通省都市景観大賞特別賞、土木学会デザイン賞優秀賞、東京藝術大学エメラルド賞、日本空間デザイン賞、グッドデザイン賞などを受賞。
2020~23年東京藝術大学教育研究助手。現在、早稲田大学、東京理科大学、日本女子大学、東京電機大学院非常勤講師。
主な作品に、「サンキタ広場」(2021)、「Spectra-Pass」(2021)、「まちの保育園 南青山」(2024)、「庭と織物――The Shades of Shadows <織物共同開発/空間構成>」(2024)などがある。2024年に「渋谷公園通りデザインコンペ2040」で最優秀賞を受賞した他、国土交通省都市景観大賞特別賞、土木学会デザイン賞優秀賞、東京藝術大学エメラルド賞、日本空間デザイン賞、グッドデザイン賞などを受賞。
2020~23年東京藝術大学教育研究助手。現在、早稲田大学、東京理科大学、日本女子大学、東京電機大学院非常勤講師。

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。
画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。